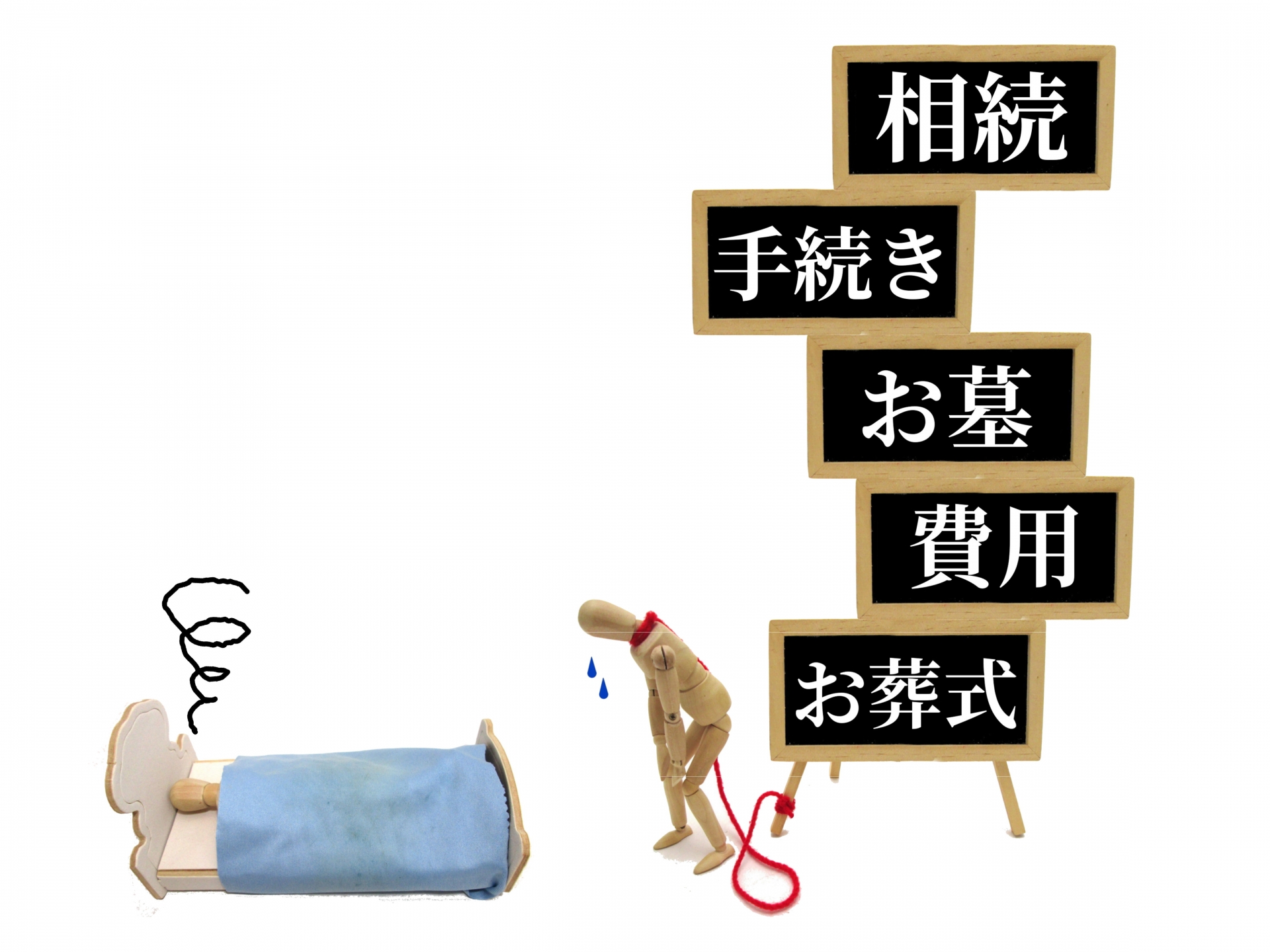相続手続きの流れと必要書類をわかりやすく解説
大切なご家族を亡くされた後、遺されたご家族には多くの相続手続きが待っています。
「何から始めればいいのか分からない」「期限があると聞いたけれど不安」——そんな方のために、相続手続きの流れを時系列に沿ってわかりやすく整理しました。
このガイドでは、死亡届の提出から相続人の確定、遺産分割協議、相続税の申告、不動産の名義変更まで、必要な書類とともに段階ごとに丁寧に解説しています。
また、各手続きの期限や注意点、相続放棄・限定承認といった判断が必要な場面についても紹介し、スムーズな相続の進め方をサポートします。
ご家族の負担を軽減し、安心して手続きを進めるために、ぜひご活用ください。
以下では、日本で一般的に必要となる相続手続きの全体像(タイムライン)と、手続きごとの主な必要書類チェックリストを「まず何をする?」「いつまで?」がひと目でわかる形で整理します。相続税・所得税(準確定申告)・相続放棄/限定承認・不動産の相続登記など、期限がある重要手続きは必ず期限内対応を意識してください。
全体像(ざっくりした流れ)
1.死亡事実の確認・死亡届提出(役所関係)
2.遺言書の有無確認(あれば内容確認/自筆証書は原則検認※保管制度利用なら不要)
3.相続人の確定(戸籍収集)
4.遺産・負債の調査(財産目録作成)
5.相続方法の選択:単純承認/相続放棄/限定承認(熟慮期間3か月)
6.被相続人の所得税「準確定申告」(4か月以内)
7.遺産分割協議書作成(または遺言どおり分割)
8.相続税の申告・納税(10か月以内)
9.各種名義変更(預貯金・証券・不動産相続登記・保険金請求・年金停止等)
10.必要に応じて家庭裁判所手続(遺留分侵害額請求等の期限に注意)
この骨格を念頭に、以下で期限順に詳しく見ていきます。
期限でみる相続手続きタイムライン(目安)
手続き別:主な必要書類チェックリスト
個々の金融機関・自治体・資産種類により追加資料が求められることがあります。以下は代表例・典型例です
1. 相続人・遺言確認フェーズで集める基本書類
| 書類 | 用途の例 | 取得先・備考 |
| 戸籍謄本(被相続人・出生→死亡まで) | 相続開始事実・相続関係証明 | 本籍地市区町村。広域交付制度により一部最寄り役場で請求可(制限あり) |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人確定 | 市区町村。取得時期は被相続人死亡日後のものが求められるケース多い |
| 遺言書(自筆/公正証書/法務局保管) | 分割方法確定 | 自筆証書は開封前に家庭裁判所で検認(保管制度利用または公正証書は検認不要) |
| 法定相続情報一覧図(任意) | 各手続きで戸籍束の代替として添付省略可 | 法務局で申出 |
2. 相続放棄・限定承認(3か月以内)
共通ポイント:家庭裁判所へ「申述」。熟慮期間内に決められない場合は伸長申立て可
主な提出物(裁判所指定書式あり):
• 相続放棄(申述書、被相続人の戸籍(除籍)・住民票除票等、申述人の戸籍、収入印紙・切手)
• 限定承認(申述書、戸籍関係、財産目録、収入印紙等/相続人全員共同)
詳細は管轄家庭裁判所案内を参照。
3.被相続人の所得税「準確定申告」(4か月以内)
主な添付・準備資料:
• 準確定申告書本体・付表(相続人等氏名・続柄記載)。
• 被相続人の収入資料(源泉徴収票、年金支払報告、配当・不動産収入記録等)を基に作成。
• 還付を代表者が受ける場合の委任状。
• 相続人等の署名押印(連署)または代表提出方法に注意。
4.遺産分割協議書作成時にそろえるもの
• 遺産分割協議書(相続人全員署名+実印押印)。
• 相続人全員の印鑑証明書。
• 相続関係説明図(添付で戸籍原本還付が楽になる実務慣行)。
• 戸籍束(被相続人出生~死亡、相続人分)※登記等で流用。
5.相続税申告(10か月以内)
申告書様式に沿って添付する代表例:
• 相続人・被相続人を証する戸籍関係書類。
• 財産評価資料(固定資産評価証明、登記事項証明、預貯金残高証明、有価証券残高、保険金支払通知、非上場株式評価資料、負債証憑、葬式費用領収書等)。
• 遺産分割協議書または遺言書写し。
• 税額控除・特例(配偶者軽減・小規模宅地等)適用の添付資料。
6.不動産の相続登記(3年以内義務/できるだけ早く)
申請類型別・主な必要書類(抜粋):
A. 遺言による相続登記
• 被相続人死亡記載の戸籍(除籍)
• 取得者(相続人)の戸籍(死亡日後取得)
• 被相続人の住民票除票 or 戸籍の除附票(住所つなぎ)
• 固定資産評価証明書(申請年度分)
• 登記申請書
• 遺言書(自筆は検認済証明/保管制度・公正証書は検認不要)
B. 遺産分割協議による相続登記
• 被相続人:出生~死亡までの全戸籍(除籍・改製原含む)
• 相続人全員の戸籍(死亡日後発行)
• 被相続人の住民票除票(または除附票)
• 不動産取得相続人の住民票(または附票)
• 固定資産評価証明書(申請年度)
• 登記申請書
• 遺産分割協議書(相続人全員実印)
• 相続人全員の印鑑証明書
• 相続関係説明図(任意)
C. 法定相続分による相続登記
(協議まとまらない場合等)
• 被相続人:出生~死亡戸籍一式
• 相続人全員の戸籍
• 被相続人住民票除票(または除附票)
• 相続人全員住民票(または附票)
• 固定資産評価証明書
• 登記申請書
• 相続関係説明図(任意)
よく使う補助資料(資産別)
| 資産区分 | 主な確認資料 | メモ |
| 預貯金 | 通帳、残高証明書 | 金融機関凍結後、相続手続依頼書+相続書類一式が必要 |
| 有価証券(証券会社口座) | 残高報告書、取引報告書 | 各社指定の相続手続キット。遺産分割確定が前提になること多い |
| 生命保険 | 保険証券・死亡保険金請求書 | 多くは請求期限あり(保険約款)。早期請求が望ましい |
| 年金関連 | 年金受給者死亡届、未支給年金/遺族年金請求書 | 期限がある制度も。10〜14日目安で停止手続き |
| 不動産 | 登記事項証明書、固定資産評価証明書 | 相続登記義務化に注意(3年以内) |
町田・相模原で相続・遺言の無料相談ならわかば相続センター
相続税申告が必要かどうかわからない方でも、税理士法人わかばの相続チームが相続税に関する相談を受け付けています。相続税申告の必要性の判断から手続きのサポート、節税対策のアドバイスまで、専門知識と経験を活かした信頼できるサービスを提供します。相続に関する不安や疑問を解消し、円満な相続手続きを実現するために、ぜひ私たちにお任せください。初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
わかば相続相談センターでは初回無料相談を実施しています。
税理士法人わかばは25年以上町田・相模原を中心に営業をしております。お客様にとって、「顔の見える仕事」を大切に、専門家チームが責任を持って直接相談に応じます。
無料相談を活用することで、相続に伴う負担を最小限に抑える方法や、節税の手段についてのアドバイスを受けることができます。早めの相談で、円滑な手続きと最適な対策を見つけましょう。
お問い合わせはこちら
税理士法人わかば(わかば相続相談センター)
0120-152-575
受付時間:平日9:00〜18:00