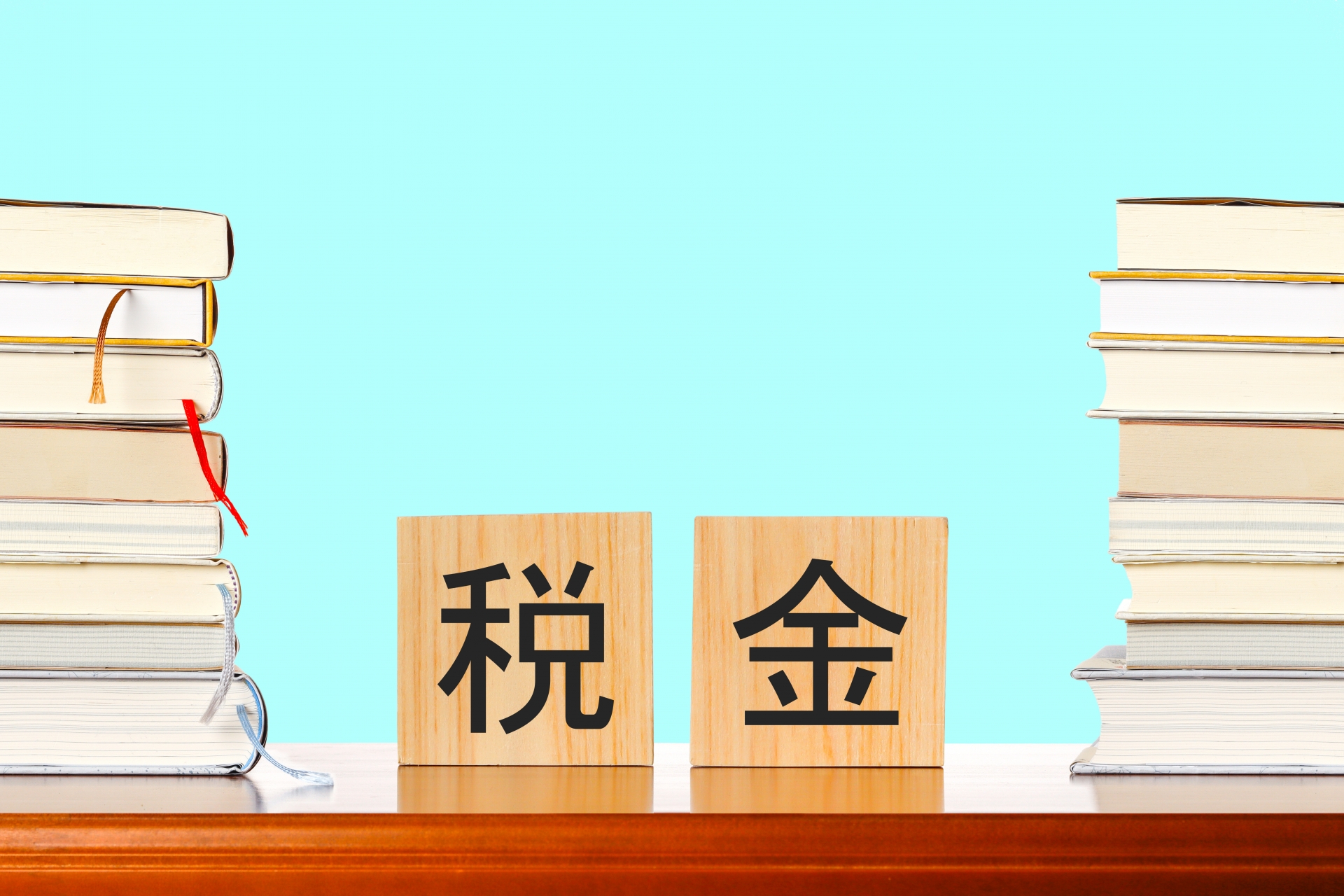相続税っていくらかかる?わかりやすく解説
「相続税って結局いくらかかるの?」「自分も支払うことになるの?」
相続に直面すると、誰もが疑問や不安を感じます。
相続税には、課税の対象となる財産・非課税の財産・基礎控除・税率など、さまざまなルールがあります。この記事では、相続人の基本から、課税される財産・計算方法までを初心者にも分かりやすく解説します。
相続税っていくらかかる?相続人・課税財産・基礎控除・計算方法までわかりやすく解説
1. 相続人とは?
相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を法律上受け継ぐ権利がある人のことです。誰が相続人になるかは、民法によって次のように決められています。
■ 法定相続人の範囲と順位
| 順位 | 相続人になる人 | 補足 |
| 第1順位 | 子(実子・養子、代襲相続の孫など) | 子が亡くなっている場合は孫が代襲相続 |
| 第2順位 | 父母(直系尊属) | 第1順位がいないときのみ相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(甥・姪は代襲相続) | 第1・2順位がいないときのみ相続人になる |
| 常に対象 | 配偶者 | 他の順位と関係なく、常に相続人 |
2. 法定相続分とは?
法定相続分とは、法律で定められた「相続人ごとの取り分(割合)」です。相続税の計算時には、この割合に従って仮の分割を行い、税額を計算します。
■ 主なケース別 法定相続分の早見表
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
| 配偶者と子1人 | 配偶者:1/2、子:1/2 |
| 配偶者と子2人 | 配偶者:1/2、子:1/4ずつ |
| 配偶者と直系尊属(例:父母) | 配偶者:2/3、父母:1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4 |
| 子のみ(配偶者なし) | 子全員で均等に分ける |
| 子なし・配偶者のみ | 配偶者が全額相続 |
この法定相続分は、実際の遺産分割の参考にもなりますが、相続税の計算時には仮にこの割合で分けたものとして税額を算出し、あとで実際の分割に応じて再配分されます。
3. 相続税が課税される財産とは?
相続税は、相続人が受け取った「一定の財産」に対してかかります。財産の種類は多岐にわたります。
■ 課税対象となる主な財産
| 種類 | 具体例 |
| 不動産 | 土地・建物(自宅、別荘、賃貸用不動産など) |
| 金融資産 | 預貯金、有価証券(株式・投資信託など) |
| 動産 | 宝石・貴金属・車・骨董品など |
| 保険金 | 生命保険金(※みなし相続財産として扱われる) |
| 退職金 | 被相続人の死亡により支給される退職金など |
| 負債や葬式費用 | 財産から控除できるが、課税評価の対象に含まれる |
■ 非課税となる財産
以下の財産は、相続税が課税されません。
| 非課税財産 | |
| 墓地・仏具・祭具 | 日常礼拝用のもので商業用でない限り非課税 |
| 生命保険金の非課税枠 | 500万円 × 法定相続人の数まで非課税 |
| 退職金の非課税枠 | 500万円 × 法定相続人の数まで非課税(死亡退職金の場合) |
| 公益事業に使われる寄付等 | 一定の条件を満たす寄付財産は非課税 |
4. 相続税の基礎控除とは?
相続税は、一定金額(基礎控除)を超える財産があるときにだけ課税されます。
■ 基礎控除の計算式
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例: 相続人が配偶者と子2人 → 相続人は3人
→ 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
この金額以下であれば相続税はかかりません。
5. 相続税の計算方法(5ステップ)
ステップ①:遺産総額の把握
すべての財産を洗い出して、正味の遺産総額を計算します(=総財産 - 借金・葬式費用など)。
ステップ②:基礎控除を引く
ステップ①で出した遺産総額から、基礎控除額を差し引きます。
ステップ③:法定相続分に従って仮の分配
実際の相続分とは関係なく、法定相続分で分けたと仮定して、各人の取得額を算出します。
ステップ④:各人の取得額に応じて税率を適用
| 課税価格(取得額) | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
ステップ⑤:実際の取得分に応じて調整
最終的な遺産分割に基づいて、実際の納税額を各相続人ごとに計算し直します。
6. 相続税の軽減・特例制度
税負担を軽くする制度も活用可能です。
配偶者の税額軽減:配偶者が取得した財産が法定相続分または1億6,000万円以下であれば非課税。
小規模宅地等の特例:自宅や事業用の土地については、最大80%の評価減が受けられる。
未成年者控除・障害者控除:対象の相続人に対して税額控除がある。
7. まとめ:相続税は「人」「財産」「制度」で大きく変わる
相続税は、相続人の人数や財産の種類、分割方法、適用できる特例によって大きく変わります。
✔ ポイントまとめ
・相続人の範囲は法律で決まっている。配偶者は常に相続人。
・法定相続分は、税計算や遺産分割の基準となる割合。
・課税財産、非課税財産を正確に把握することが重要。
・基礎控除を超える場合にのみ相続税がかかる。
・特例や控除制度を活用すれば、税額は大きく軽減可能。
町田・相模原で相続・遺言の相談ならわかば相続センター
相続税申告が必要かどうかわからない方でも、税理士法人わかばの相続チームが相続税に関する相談を受け付けています。相続税申告の必要性の判断から手続きのサポート、節税対策のアドバイスまで、専門知識と経験を活かした信頼できるサービスを提供します。相続に関する不安や疑問を解消し、円満な相続手続きを実現するために、ぜひ私たちにお任せください。初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
わかば相続相談センターでは初回無料相談を実施しています。
税理士法人わかばは25年以上町田・相模原を中心に営業をしております。お客様にとって、「顔の見える仕事」を大切に、専門家チームが責任を持って直接相談に応じます。
無料相談を活用することで、相続に伴う負担を最小限に抑える方法や、節税の手段についてのアドバイスを受けることができます。早めの相談で、円滑な手続きと最適な対策を見つけましょう。
お問い合わせはこちら
税理士法人わかば(わかば相続相談センター)
0120-152-575
受付時間:平日9:00〜18:00